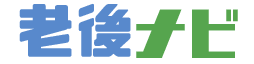アルツハイマー病とは
アルツハイマー病は、進行性の病気で記憶力や思考力が徐々になくなっていき、最終的には生活する能力も失われる病気です。
60歳以降の高齢者にこの症状が初めて現れることが多く、高齢者における認知症の一般的な要因と言われています。
この疾患は、病気を発見したアロイス・アルツハイマー博士の名にちなんで命名されています。
脳内におけるアミロイド班や神経原線維変化は、主なアルツハイマーの特徴とされており、それ以外にもは、ニューロンの連結が消失してしまうこととなります。
人により、治療によって病状の進行を抑えることができますが、現状この疾患に対する治療法は発見されていません。
アルツハイマー病の人の脳
アルツハイマー病による脳の障害は、症状が出るもっと前から始まっていると言われています。
タンパクが異常沈着を起こし、脳の至るところにアミロイド班が生じ、神経原線維変化が起こることで、ニューロンの機能が徐々になくなっていきます。
最終的には、ニューロンは相互機能、連結の力を失ってしまい、最終的には死滅してしまいます。
病変は、脳内での記憶形成に必要不可欠とされている海馬と呼ばれる構造体に広がっていきます。
アルツハイマー病が進行していくと、ニューロンの死滅に伴い、脳組織の委縮が進んでいき、それによる障害も大きくなっていくのです。
分かりやすい例ですと、身体が動かなくなってしまうことや、いつ食事をしたのかも分からなくなってしまうことなどです。
場合によっては、自分が誰なのかも分からないといった、記憶障害が起こる場合もあります。
治療については発症してしまうとどうすることもできない指摘を受けています。
アルツハイマー病の生存率
アルツハイマー病の進行速度はゆっくりです。
症状の認められない初期段階、軽度認知障害と言われる中期の症状、アルツハイマー病と呼ばれる認知症といった病期での進行となっています。
アルツハイマー病と診断されてから死亡するまでの期間は人それぞれで、認知症と診断された時点での年齢が80歳以上の場合はわずか3年から4年、80歳以下の場合は10年以上とも言われています。
認知症は、認知機能や行動能力が普段の生活を阻害する位に失われてしまうことを言います。
認知症の重症度は様々で、ほとんど支障がないところから、日常生活すら行えないほどの段階まで様々です。
認知症が起こる原因としては、薬物の副作用、慢性アルコール依存症、脳腫瘍・脳の感染症など様々なものがあります。