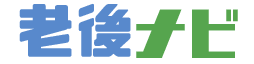肺炎とは
肺炎は、いろいろな病原菌に感染してしまうことにより、肺に炎症を起こしてしまっている状態を言います。
体力が落ちている時はもちろんですが、高齢者は免疫機能が低下していることが多いですが、こうした場合にかかりやすいことが知られています。
肺炎は、細菌やウイルスが体内に入ることにより起こるのですが、健康な人であれば、病原菌の除去が可能です。
しかし、風邪により喉に炎症が起こっている状態ですと、病原菌がそのまま侵入してしまい、肺に炎症が起こってしまうのです。
風邪にかかったら肺炎になってしまう、ということではなく、侵入してきた病原菌の感染力が免疫力を上回った場合に発症することが確認されています。
肺炎にかかった場合、その死亡率は約9%であり、死因順位は過去20年間をさかのぼると第4位に位置しています。
肺炎の症状と診断
肺炎になると、せきや発熱、胸痛や悪寒、呼吸困難などが起こります。
この症状は数日続きますが、高齢者の場合はこれらの症状ではなく、元気がない、食欲不振などの症状だけが出ることもあるため、注意が必要となります。
肺炎の診断は、胸部X線検査、血液検査、病原菌の特定の3つになります。
肺炎が疑われる場合、胸部X線検査を行い、更に血液検査を行った上で判定をします。
重度な場合には、病原菌の特定も同時に行われます。
この特定は、抗菌薬で適切なものを用いるために行われます。
肺炎の治療法
肺炎の治療は、軽症および、脱水を伴わない場合は外来治療が行われ、重症例となると入院治療が行われます。
65歳以上の高齢者の場合、通院が困難なこともあり、そうしたケースにおいては入院治療が行われることとなります。
一般的には適切な治療が行われた場合、1週間から2週間で治癒となりますが、免疫力が低下している状態、高齢者、または複数の病原菌に感染している場合、症状が重くなることにより死亡する場合があります。
せきや淡に対しては、対症療法が行われます。
また、発熱や炎症に対する治療も行われ、患者への負担を軽減させます。
高齢者や小さな子どもの場合、免疫力が十分でないケースがあり、その場合はちょっとした風邪であっても、肺炎に繋がることがあります。
肺炎になり、細菌がそのまま脳や心臓に行ってしまうと、合併症となりそのまま命を落とす可能性も出てきます。
これらの年代の世話に関しては、慎重に行い、少しでも肺炎発症のリスクを下げる努力をしてあげることが大切です。