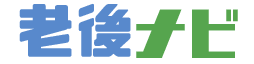脳卒中について
脳卒中には種類がいくつかありますが、大きく分けると脳の血管が詰まってしまう脳梗塞、脳の血管が破れることで出血が起こる脳出血、くも膜下出血に大別できます。
血管が詰まってしまう病気は、脳梗塞、脳血栓症、脳塞栓症、一過性脳虚血発作です。
血管が破れてしまう病気は、脳出血、くも膜下出血があります。
いずれの病気も、脳に異常が起こる病気のため、発症してからは時間との勝負となります。
一般的には30分以内に処置出来れば生存できる可能性があるとされていますが、後遺症が残る可能性もあります。
病気が起こった部位によっては、身体が動かなくなることもありますし、最悪のケースとして寝たきりになってしまうこともあります。
後遺症が起こってしまうと、リハビリを行うことによって、多少症状を軽減することもできますが、多くの場合は重篤な症状はそのまま残り、予後も期待できません。
だからこそ、発症をできる限り未然に防ぐ努力が必要となってくるわけです。
脳卒中の現状
現在、脳卒中の患者数は150万人と言われています。
毎年の発症者は25万人と推測されており、多くの人が命を落としていると言われています。
その証拠に、脳卒中はがんや心臓病に次いで、日本人の死亡原因第3位となっているのです。
脳の血管が弱っていると、それだけ発症するリスクも高くなるため、高齢者の方が発症するケースも珍しくありません。
生活習慣病の1つとも言われており、年齢に関係なく発症する可能性もあるため十分な注意が必要となります。
脳卒中の予防
脳卒中は一度発症してしまうと、とても危険な病気ですが、検査を行うことで予防が可能です。
脳卒中の危険因子は簡単な検査を行うことで分かるからです。
検査によって危険因子が分かれば、生活習慣の早期改善もできますし、適切な治療を受けることもできます。
早ければ早いだけ生存率も伸びますし、発症前の状態まで回復できる可能性があります。
ただし、間に合わなければそれなりのリスクを負う可能性もあるのです。
加齢や遺伝による脳卒中の治療は難しいですが、それ以外の因子を治療することにより、十分に脳卒中の予防を行うことができます。
MRI検査によって、隠れ脳梗塞と呼ばれるものが見つかることがありますが、こちらの方が発症するリスクが高いと言われています。
もしも何かしら軽い症状が見つかったのならば、一刻も早く専門機関で検査を受けることが大切で、それだけで後遺症や死を免れることができるようになります。