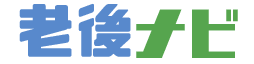糖尿病とは
糖尿病とは、ブドウ糖が細胞の中に運ばれることなく、血液の中にあふれてしまう病気です。
これは、血糖値を下げる働きを持つホルモンである、インスリンの働きが細胞に作用しなくなることが原因とされています。
インスリンは、体内の血糖値を下げる働きを持つ唯一のホルモンで、血糖値が食後にあがらないように調節してくれます。
このインスリンの働きがブドウ糖をコントロールしているわけですが、これが上手く作用しなくなってしまうと、ブドウ糖が細胞に取り込まれなくなります。
血液中のブドウ糖が使えなくなってしまうことにより、血糖値が上がってしまい、全身のエネルギーが足りなくなってしまうこととなります。
インスリンがすい臓から分泌されない、量が不足している、分泌されているにも関わらず十分な作用がないといった要因が元で高血糖となるのが糖尿病です。
糖尿病の種類
糖尿病には4つのタイプがあります。
1型糖尿病と呼ばれる、インスリンをすい臓が作らなくなることにより、身体の中のインスリンの量が全く足りなくなってしまう糖尿病のことです。
2型糖尿病は、インスリンの量が不十分になることで起こるものと、ブドウ糖がうまく取り入れられなくなることにより起こる糖尿病があります。
食事や運動と言った生活習慣が関係していることが多く、日本での糖尿病患者のほとんどがこのタイプとなっています。
また、遺伝子や免疫の異常、感染症を含めた他の病気、あるいは何らかの薬品が原因となって起こる糖尿病もあります。
これ以外には、妊娠時に起こる、妊娠糖尿病と呼ばれるものもあります。
糖尿病の症状と治療
糖尿病の症状は、のどが渇く、尿の量や回数が増える、全身の倦怠感、体重の急激な減少、たちくらみ、手足のしびれ、性欲減退、月経異常などが挙げられます。
糖尿病の症状は、初期症状などがないため、治療の必要があるとしても受けない人が大多数を占めています。
しかし、本当に恐ろしいのは、糖尿病が原因で引き起こされる合併症で、最悪の場合、死に至るケースもあると言われているため、そうならないようにきちんと治療を行うことが大切です。
糖尿病の治療には、初期段階であれば食事療法や運動療法、進行した状態であれば薬物療法が行われます。
食事療法の場合、自分に合った食事を行い、必要とする栄養素を取るようにする工夫が必要となります。
運動療法は、医師の指示に従い、適切な運動メニューの元運動を行うことになります。
薬物療法では、インスリン注射が行われ、特に体内でインスリンが作れない1型糖尿病に対しては必ずこれが必要となり、それ以外の糖尿病においても、改善が見られない場合薬物療法が行われます。